月曜は、『読んだ本シリーズ』。
今週の本はこちら。
データ、根拠、分析・・・・
そういった言葉から離れて議論がなされ決定されていきがちな『教育』について、
データに基づいてアプローチする経済学者の本です。
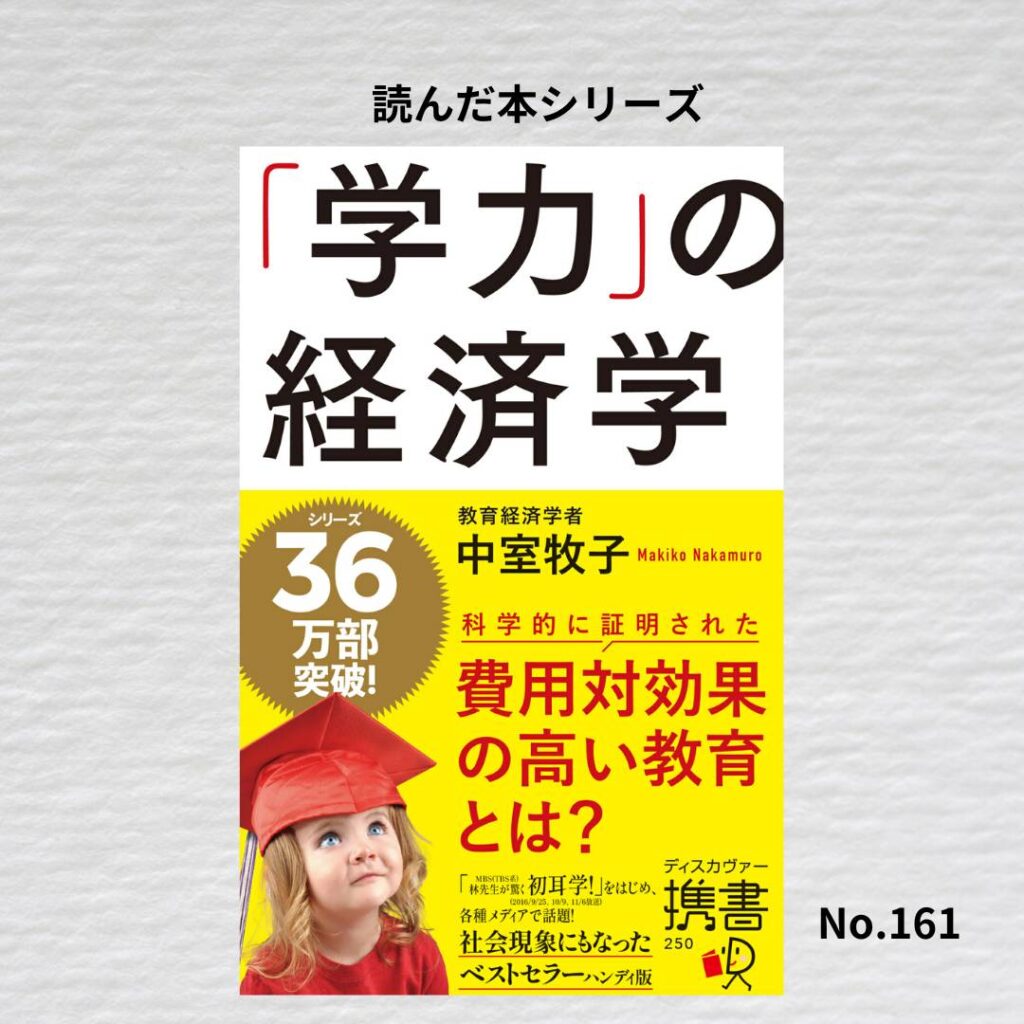
「学力」の経済学
中室 牧子 (著)
・エビデンスとは?教育政策では、科学的な根拠が必要だとは思われていない。
根拠とするべきは、個人の体験記ではない。
「私の経験では」と、主観的な持論を展開するのは、
財政、経済ではありえない光景。
行政の会議では
「活気にあふれている」「満足した」など、
人によって見方が変わる主観的な表現で効果をはかっている。
それはエビデンスとは言えない。
・自尊心は結果にすぎない。「自尊心を高めれば子どもが育つ」という論は、因果関係が逆。
そもそも、因果関係と相関関係の定義を意識することが必要。
「自尊心が高まれば、子どもたちを社会的なリスクから遠ざけることができる」
という有力な科学的根拠は、ほとんど示されなかった。
「学力が高いという原因が、自尊心が高いという結果をもたらしているのだ」
と、因果関係は逆であるとする説を出した教授も。
学生の自尊心を高めるような介入は、学生たちの成績を決して良くしないことが示された。
逆に、事実を反省する機会を奪い、自分に対して根拠のない自信をもつことにつながり、
むやみに子どもを育てることが、実力の伴わないナルシストを育てることになりかねない。
・非認知能力は、将来に大きく影響する。学校は非認知能力を培う場所でもある。
学校に行かずに高卒認定を取得した子は、高校を卒業した子に比べて
年収や就職率が低い傾向がある。
認知能力(学力など)のみが重要なのであれば、大きく差がつくはずがない。
どんなに勉強ができても、一歩学校の外に出れば
学力以外の能力が圧倒的に大切だというのは、多くの人が実感しているところ。
非認知能力が、人生において極めて重要。
誠実さ、忍耐強さ、社交性、好奇心の強さ、、、
これら非認知能力は、人から学び、獲得するもの。
おそらく学校は、これを培う場所でもある。

教育についてはあまり検証をしない(というより、検証は一生懸命してくれているようだが、検証とは呼べないような主観的なものが多い)
とよく不思議に感じていた私のモヤモヤをスッキリさせてくれる本でした。
(もちろん、短絡的な原因と結果の追求をしすぎて教育のおおらかさやパフォーマンスを落とすことはあってはならないのですが)
『因果関係』と『相関関係』の話は、私も教育に関する
会議や人の話を聞く中で意識しているところ。
これが明確ではなく話されているところにヒントがあるようにも感じる。
やはりたくさんのサンプルから体系的に検証して考えたものをもとに
戦略を考えたいところ。
日本では教育に差をつけて(『実験』などと言って)
因果関係を調べてみるというのが難しいようにも感じますが、
『○○モデル校』のように、学校の特色を出す中で検証がしていけたら。
教育行政に関わる私としては、自身への戒めとして手元に置いておきたい本でした。

経営者さんと関わる者として
ビジネス系、組織論系、経営論系・・・に留まらず、小説、学術系まで。
『雑食読書』の鈴木が毎週1冊本をご紹介いたします。