月曜は『読んだ本シリーズ』
先輩(親くらいの年齢の男性)と電車で話しているときに
「最近読んだ本で面白い本があった」
という話になり
「ゴリラとしてゴリラと暮らした人」
「京大の教授(総長も務めた)」
というパワーワードと共にご紹介いただきました。
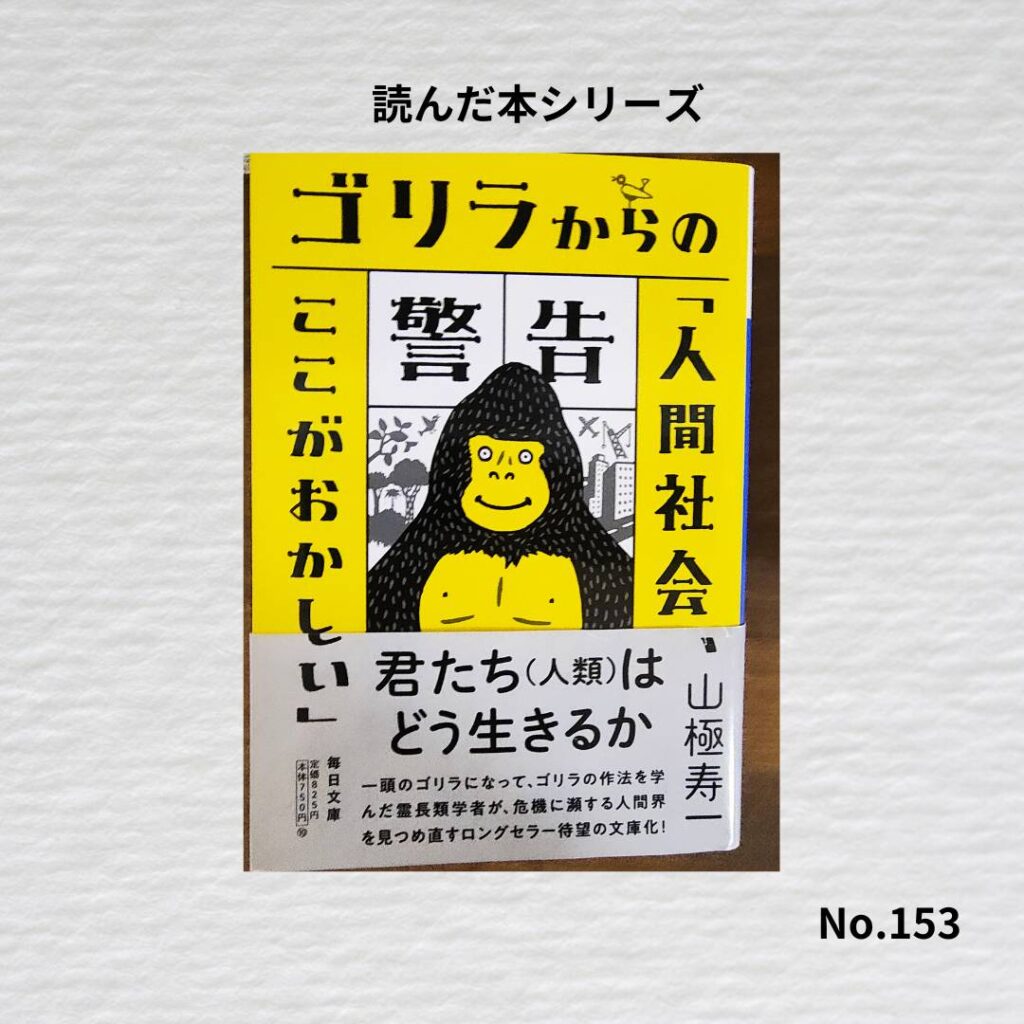
ゴリラからの警告「人間社会、ここがおかしい」
山極 寿一 (著)
・現代社会の大人の在り方
人間とゴリラの子どもの違いとして、
「なりたい」、「知りたい」という欲求が挙げられる。
その望みを叶えるための方法が
「憧れの人に会う」、「その知識や経験をもつ人に聞く」
だった昔は、大人が子供から信頼されており、
大人が子どもを教育できる関係性があったわけだが、
インターネットの発達により
現代の子ども達は、知りたいことを人から学ぶ必要がない。
知識や経験があるだけでは、大人は信頼されなくなった。
現代は、知識ではなく、実践する力や考える力を教える時代だ。
人と出会い、実践の場に参加しなければならない。
他者のなかに自分を見つける楽しさを教えていきたい。
老人の存在が、
対立を解消し、束縛から人間を救ってきたという話とも合わせて
大人としての在り方を肝に銘じたいところ。
・ゴリラの民主主義
ゴリラのリーダー(体の大きなオス)が行く方にメスや子ども達が続く。
ついていかないのは、よく知った場所で危険がないと判断しているとき。
バラバラに動いていてもやがて声が多い方向にまとまって歩き出す。
そのような場合はリーダーが慌てて引き返してくるそう。
人間はどうか。
平和なときはそれぞれが勝手に行動し、
でも不安だから人数が多い方へ同調する。
さらに不安になると強いリーダーを求め、そのリーダーの方へ歩む。
人間も同じだが、もはやどの方向に声が多いのかわからなくなっている。
無名のささやきに踊ったりする。
また、リーダー(現代の政治家)は、うしろを振り返らない。
ドラミング(虚勢を張る)のはうまいが、みんなが違う方向へ歩き出しても
自分の方向を変えない。
もはや人間はゴリラの民主主義すら行使できなくなっている。
・言葉をもつ人類が見落としているもの
言葉をもたないゴリラには善も悪もない。
自分に危害を加える者には立ち向かうが、
世代間で怨念を継承することがない。
人間は言葉をもっている生物で、話をつくらずにはいられない。
世界を直接見ているわけでなく、
言葉によってつくられた物語の中で世界を見ている。
依然、世界では和解の席に着こうとしない争いが多いが、
言葉や文化の壁を越えて行き来してみると、
どこでも人間は理解可能で温かい心をもっていることに気づかされる。

そもそも人間が人間として生活をはじめる前から考えれば
実に奇妙な習慣をつけてしまったこと、
我々人間や類人猿がもっていた機能を
現代社会で取りこぼしてしまっていることなど、
たくさんのことをゴリラから学ぶことができる一冊でした。

経営者さんと関わる者として
真面目なビジネス系、組織論系、経営論系・・・に留まらず、小説、学術系まで。
『雑食読書』の鈴木が毎週1冊本をご紹介いたします。